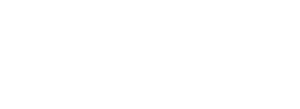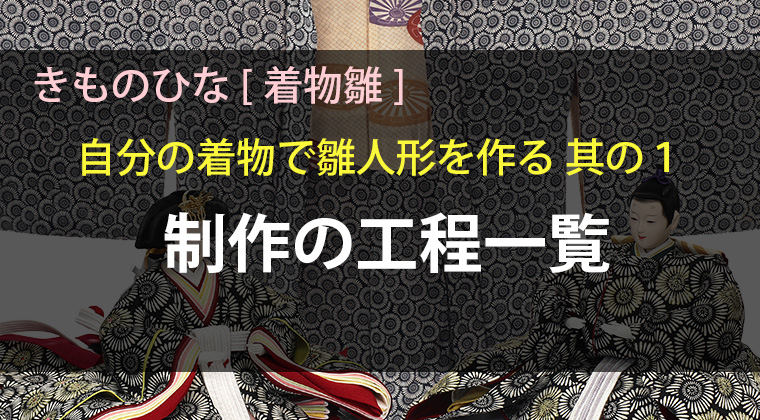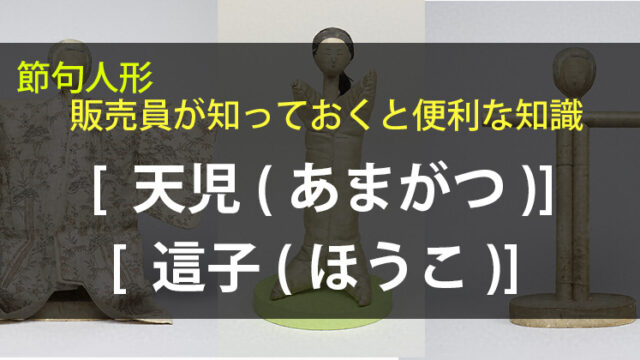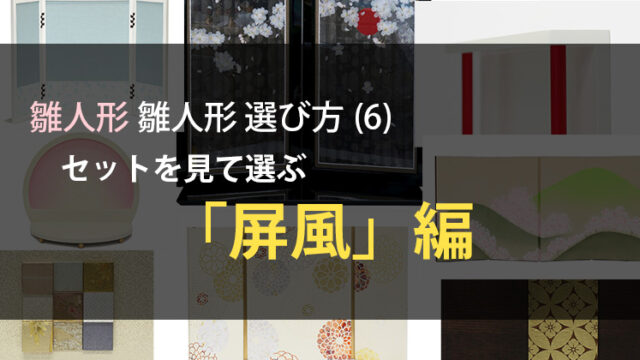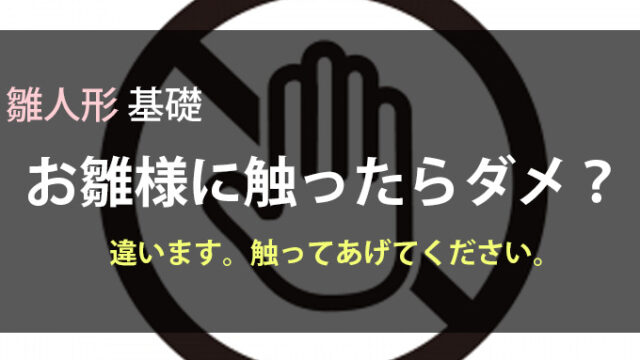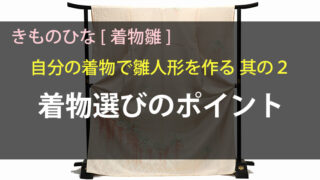「ひなのすすめ」では、
ご自身が着ていた思い出の着物を使って、自分自身の雛人形をつくるという企画を行っています。
着物の種類はといません。
思い出の着物でも、思い出はそれほどないけど着る機会もないという着物でも、
タンスに眠ったままの着物でも、ご家族の方から譲り受けた着物でも、
また、
反物のままであっても、羽織であっても、七五三用の子供用であっても、
正絹でも、化繊でも、
織物でも、染物でも、紬でも、
「この着物をつかってお雛様がつくれたら」
という思いがあれば、それは、あなただけの雛人形を作ることができる着物です。
これから、数回に分けて、着物雛を作る工程をご案内したいと思います。
着物の雛人形を作るというのは、職人や工房にすべてお任せるするという事ではありません。
もちろん、お忙しい方であれば、すべてプロの経験にお任せという事も可能です。
また、反対に、着物のどこの柄を雛人形に使いたいという要望や、
雛人形の重ねの色のパターン、雛人形の帯の色など、お客様が参加しながら決めていける工程もあります。
ご自身のお雛様の制作に携わるという体験は、きっと大切で豊かな時間を感じることが出来るでしょう。
それを、一つの体験記として紹介していきたいと思います。
きものひな 作る工程の案内
1,工程の一覧を把握する(この記事に当たります)
2,きものを選ぶ
まずは、やはり雛人形そのものとなる着物(その他好きな生地)を選びます。
https://hinano-susume.com/blog/select-kimono-for-hinadoll/
3,雛人形の衣装となる部分を着物から選び出す。
つぎに、その着物から、雛人形のパーツごとに柄を取る構想を考えます。
https://hinano-susume.com/blog/select-kimono-for-hinadoll-3/
4,着物の撮影をする
雛人形を作る前に、着物の写真を残します。
裁断後の作業において、何度か裁断する前の状態を確認したいことがあります。
そういった場合に参照できます。
5,着物を解き、型紙から、雛人形のパーツを作っていく
6,仕上がったパーツをもとに、姫の重ねや殿の単の色を決めていく
7,着せ付けをし、後付けのパーツ(帯や裳)を決める
8,完成した雛人形の写真撮影をする
9,お客様への出荷準備・出荷・お届けする
10,<後日>着物と雛人形のフォトブックを制作し、お届けする
大体このような流れとなります
これらを、順を追ってブログでご案内をして行きます
※工程によっては、公開ができない作業もありますので、なるべくくわしい文章でお伝えできるようにいたします。
今年もすでに何名かの方の作業に入っておりますが、皆さまとても楽しみにお雛様の仕上がりを待ってくださっております。
ぜひ、ブログの内容をお読みいただき、作業工程のご理解を頂けますと、一層お雛様に愛着がわくと思います。
なるべく頑張って更新いたしますので、気長にご覧いただけると幸いです。